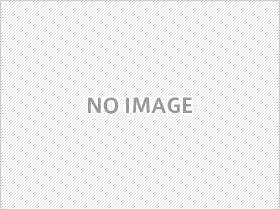イラスト:ソリマチアキラ
時は1999年、大阪ミナミの下町で、Aクリニックが院外処方箋を発行することになった。
院長のA先生は消化器内科が専門で、内科を標榜。奥さんが小児科医で、さらに医局から内科医師が派遣で来ており、1日の処方箋枚数が100枚を下らない大型診療所だ。
院長はまだ60歳すぎの働き盛り、さらに息子さんが医大生──。薬局を出店する側からすると、長期安定が見込める好条件だ。まさに分業ラッシュの時代、どこの薬局もこのクリニックの門前を狙っていた。
A先生は昔気質の怖い人で、いつも怒っていた。私は、かつてMR時代に鍛えた“腕”を生かして、あの手この手でアプローチしたが、A先生は私の名前すら覚えてくれない。脈なしかとあきらめかけた頃、「夜遅くまで働くスタッフはいるのか」とか「土日は対応してくれるのか」と聞いてくるようになり、ある日突然、「あんたとやる」と一言。
そこからはトントン拍子で話が進んだ。当時は結構あったと聞くリベートを要求されることもなく、無事に開局。特にトラブルもなく、経営もすぐに軌道に乗った。
そんなある日、A先生が癌だという知らせが舞い込んだ。A先生は入退院を繰り返すようになり、休診が多くなった。さらに、派遣医師の診療日数も、毎日から週に4日になり、2日になり、それに伴って処方箋がみるみる減っていった。
そうこうするうちにA先生が亡くなった。ついに派遣医師は来なくなり、奥さんが細々と小児科を続ける程度に……。処方箋枚数は激減し、家賃と人件費を考えると、もう薬局を閉めるしかないと思い始めていた。そんなとき、奥さんがうれしそうに知らせてくださった。「息子が戻ってくる」。
「まさに救世主。助かった!」。私は心から、奥さんに「本当に良かったですね」と話した。が、続く奥さんの言葉を聞いて絶句した。
「息子は産科でね」
えっ?!サ・ン・カ──。鉄剤ぐらいしか出ないじゃないか。せめて婦人科もやってくれていれば(涙)。
薬局を閉めることも考え始めていたが、息子さんが帰って来るということで、閉めるに閉められなくなった。もちろん産科医でも、いないよりはましだ。奥さんも息子さんが帰ってきて、やる気になったのか、処方箋が少しだが増えた。
そんなとき、また奥さんがうれしそうに知らせてくださった。「実は、息子が結婚することになったの。お嫁さんはお医者さんなのよ」。
「助かった! やっぱり医者家系は強い!」。私は心の底から、奥さんに「本当に良かったですね」と伝えた。が、続く奥さんの言葉を聞いて、またもや絶句した。
「お嫁さんは麻酔科なのよ」
えっ?!マ・ス・イ・カ──。そりゃ、病院では、産科医と麻酔科医は一緒に仕事をすることも多く、出会いがあるのは分かるけれど、よりによって、薬局にとって“最悪”な組み合わせ、「産科の息子に、麻酔科の嫁」で戻って来なくても(涙涙)。
その後しばらくして、息子さんが産科クリニックとして正式に承継、奥さんは引退した。かくして、わが薬局も、引退の運びと相なった。
いつの時代も、そして今後も、マンツーマン分業の場合、薬局はクリニックと一蓮托生。クリニックの行く末に大きく振り回される。今、処方箋がたくさん出ている、息子が医大生、という好条件だからといって、社長は決して安心してはいけないのである。(長作屋)
(「日経ドラッグインフォメーション」2013年6月号より転載)