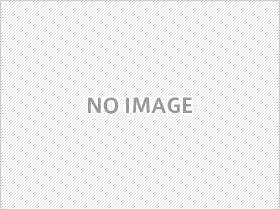Illustration:ソリマチアキラ
ある日曜日、ボクは処方元のAクリニック院長のホームパーティーに招かれた。そこにはA院長の奥さん、お母さん、叔母さん、そしてBクリニックのB院長夫妻がいた。ちなみに、A院長の奥さんは薬剤師で、ボクが製薬会社に勤務していた頃からの知り合いだ。お母さんは開業医の妻として、A院長をはじめ3人の医師を育てた。そして叔母さんは現役の開業医だ。
新築した豪邸は、玄関にピアノが置かれ、リビングは20畳超。そしてダイニングの食卓には、高級ホテルからケータリングした料理と高級ワインが並び、さらにA院長行きつけの一流寿司店の大将が寿司を握ってくれた。なんとも豪勢なパーティーだった。
ボクはニコニコしながらも、居心地の悪さを感じていた。というのも皆、和気あいあいと話をしていたが、誰もボクに話を振ってこなかったからだ。この雰囲気、どこかで経験した……と記憶をたどる。あぁそうだ、製薬会社の営業職時代だ。先生と一対一であれば、色々と話ができるのだが、複数の医師対ボクとなると途端に分が悪くなる。別に医療の話をしているわけでもないのに、話の輪に入っていけないのだ。今回もそのパターンだ。そのとき……。
「最近は、薬局も大変だよな」とB院長。待ってました!ボクは「そうなんですよ。調剤基本料というのがありまして…(略)…利益が大きく変わってくるんです」と話した。皆、「ふーん」と全く関心を示さない。ところが続けて「今後は調剤だけでなく、薬を減らすなどの処方提案ができる薬局にしていかないと、経営的に厳しく……」と話し始めた瞬間、全員の目がギラリと光り、一斉にボクに鋭い視線を送ってきた。
ボクの言葉を遮るように口火を切ったのは、A院長のお母さん。「薬剤師がどうして処方の提案なんかするの?そんなことして責任が取れるの?無責任過ぎるじゃない!」。するとB院長の奥さんも「そうよ、そんな余計なことをしているから、薬を間違えるのよっ!!」と激しい口調でまくしたてた。そう、ボクの薬局はこともあろうに、B院長のお母さんの薬を2度も間違えて交付した“前科”があったのだ。
女性陣の激高ぶりに感化されてか、男性陣からも「最近、ポリファーマシーが悪いように言われるが、現実はそんなものじゃない」「薬剤師が薬を減らすって、病態も分からないのにどうするんだ」と厳しい言葉が浴びせられた。つい先ほどまで、ここにボクの存在はなかったのに、気付くとボクは輪の中心にいて集中砲火を浴びていた。
いたたまれなくなったボクは、長い付き合いのA院長の奥さんに視線を送ったが、スッと目をそらされてしまった。「あんたは薬剤師だろうが!見捨てるなよ!裏切り者っ!」と心の中で毒づくボク。
薬剤師や薬局の仲間と話していると、減薬の提案だのフォローアップだの、臨床推論だのといったことは、当たり前のように聞こえてくる。しかし、現実には「余計なことを考えずに、とにかく早く正確に薬を出す」ことを薬剤師に求める医師(と、その妻たち!)が何と多いことか。
翌日の朝礼で、教育担当部長が「これからの薬剤師には、患者をフォローして、処方に介入していくチカラが必要です」と話したが、この日のボクの心には、むなしく響いた。(長作屋)