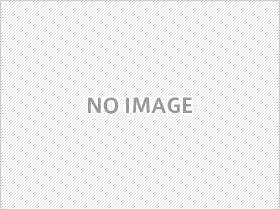Illustration:ソリマチアキラ
年末、息子と久しぶりに食事をした。そのとき唐突に、息子が「おやじの葬式は大阪でやった方がいいよね」と言ってきた。まるで天気の話でもするようにサラリと言われて、ボクは一瞬たじろいだ。えっボクの葬式のハナシ?
たじろいでいる場合ではない。「何言ってんだ。葬式は田舎の家でやるものだろ」と反撃に出た。「遠いし、会社の人たちにも迷惑がかかるよ」と息子はこれまたサラリと言う。「いやいや、みんな、駆け付けてくれるよ」と思ったものの、これ以上言うとせっかくの料理がまずくなりそうだったので、話題を変えた。
ボクの実家は関西の片田舎にある。15年ほど前に父が亡くなり、母が独りで住んでいたが、7~8年前から身の回りのことがおぼつかなくなり、今ではボクが住む街の近郊の高齢者施設に入居している。
故郷の実家には今や誰もいない。しかしボクは、1~2カ月に1回、必ず帰郷している。ボクは必ず正面玄関から「ただいま」と言って入り、まず向かうのがお仏壇。水とお線香を上げる。掃除や片付けをして一晩過ごし、出てくるときは「行ってきます」と言って後にする。
誰もいない家になぜ足しげく通うのか。理由の1つは、ボクのルーツがそこにあるからだ。そしてもう1つ、それは父の遺言だ。教員だった父が定年退職したとき、ボクは父母に遺言書を書いてほしいと話した。ボクには5歳離れた妹がいて、両親からは「兄妹仲良くしなければならない」と諭され続けてきた。今でも家族ぐるみで仲良くしているが、この先、万が一、仲たがいするようなことがあれば、そのきっかけは相続だろう。長作屋には実家と大してお金にならない田舎の土地が少しある。そこでボクは「2人がけんかしないように財産分与を書き残してほしい」と頼んだのだ。
それから20年ほどたって父が亡くなり、金庫の底に遺言書が入っているのを見付けた。そこには家と土地は全てボクに相続すると書かれていたが、なんと、次のようなただし書きが付いていたのだ。「遺言執行者の長作屋(ボク)は、相続された物件は長女(妹)の生まれ育ったふるさとでもあり、その一族の駆け込み寺としての期待が込められていることを認識し、末永く円満な交際を続けてほしい」。うーーん。
そんなこんなで、ボクは故郷に通い家を守っているというわけだ。「いつでも駆け込めるように管理しておくように」という遺言は案外、重い。築30年ほどになる一軒家はあちこちにガタが来ている。風呂や屋根の修復もした。昨年の春は西の壁、秋には南の壁の塗装をした。次の春には東の壁も塗り替える必要がありそうだ。春と秋には庭師を入れて植木の手入れもしている。そこまでしているが、引退後に住む予定もないし、息子にとっては、子どもの頃、夏休みやお正月に訪れた祖父母の家というくらいの思い出しかない。そう考えると、ボクの代で何とかしなくちゃいけないのかもしれない。
でも、葬式は別だ。大阪に働きに来ている今のボクは、むしろ"仮の姿"だ。だから家はいまだに借家で持ち家ではない。葬式は因縁のある故郷でやらねばご先祖様に申し訳が立たない……。
それにしても、周りもボクも、葬式や相続のことを考える年齢になったのだなと、しみじみ思いながらサプリメントに手を伸ばす今日この頃だ。(長作屋)