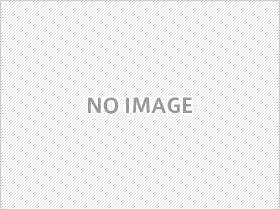Illustration:ソリマチアキラ
ある日の長作屋薬局でのこと。50代の女性患者が来局すると、同年代のパート薬剤師がフロアに出ていき、「あら~Aさん、お久しぶりやねぇ~。どうしてたん?」と親しく話しかけた。それを見て、ボクは少しうれしい気持ちになった。どのような業態であっても、店の人から親しく接してもらえれば、訪れた人は悪い気はしないはずだ。
しかし、それを良しとしない薬剤師もいる。Aさんが帰った後、対応したパート薬剤師に管理薬剤師が「患者さんには分け隔てなく平等に対応してください。特定の患者さんと親しくするのは良くないです」と注意していたのだ。
その管理薬剤師は、病院出身で10年ほど前に転職してきた40代男性だ。機械のように正確に薬剤を調製し、知識も豊富で、処方箋の疑義を見つける力も段違いに高く、処方医からの信頼も厚い。薬剤師としては完璧だが、何かが足りない。それがまさしくフレンドリーさや熱量なのだ。
もっとも、ボクは彼に前述のパート薬剤師のようなフレンドリーさを求めるつもりはない。知識ではおよばないが気遣いや優しい声かけができる薬剤師、薬局が明るくなるムードメーカー、後輩の面倒見がいい薬剤師など、それぞれでいいと思っている。もちろん、薬剤師として一定以上の医療・薬学知識は必須だ。愛想や気遣いだけでは医療職は務まらない。必要以上に患者と親しくなることで医療者としての仕事がしにくくなるのは困るが、一定の範囲内で、それぞれが持ち味を発揮すればいい。問題は、彼がそれを認めず、マニュアルのような患者対応を求めることだ。
そういえば、米国シアトル発祥で日本を席巻しているカフェチェーンは、ドリンクやフードの作り方には細かいマニュアルがあり品質管理を徹底しているが、接客に関するマニュアルは設けていないと聞く。対話を通して顧客の気持ちを汲み、必要なサービスをスタッフが考えて提供することを大事にしており、ホスピタリティを追究する上で、あえてマニュアル化していないのだとか。
ボクも利用するが、出勤時に時々立ち寄るだけの客の顔も覚えて「いつもより少し時間が早いですね」などと声をかけてくれる。ボクが薬をもらっている大手調剤チェーンのスタッフは、3年以上通っているのにいまだに親しく話しかけてくれない。雲泥の差だ。
調剤は厳格なルールの下に品質を徹底しつつ、目の前の患者に必要な対応は、スタッフがそれぞれ考えてほしい。そう思うのだが、その管理薬剤師はホスピタリティまで管理しようとする。管理者として方向性を打ち出すことは大事だが、行き過ぎるとスタッフは萎縮してしまう。実際、彼の店舗のスタッフは元気がない。黙々と仕事をしているが、決められたこと以外には取り組まず、創意工夫がなく、楽しくなさそうだ。
調剤報酬は伸びず、薬価差も絞られている今、自分たちのサービスで一人でも多くの患者に貢献するという気持ちがないと、薬局は店舗を維持することすら難しくなっていくに違いない。
以前なら、その管理薬剤師を呼んで諭していたことだろう。しかし、彼は2度ほど「転職したい」と上司に相談しているという。彼が管理職として成長する上でも言うべきと思いつつも、言葉をグッと飲み込んだ。これを読んで気付いてくれ……ないよな。(長作屋)