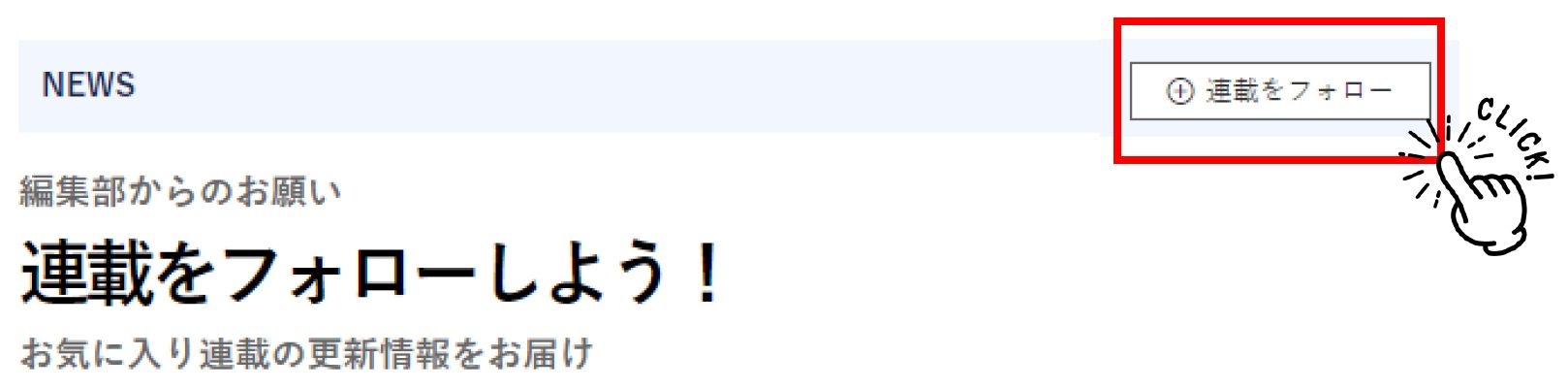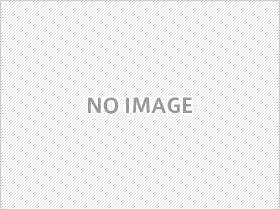イラスト:畠中 美幸
東海地方にあるA整形外科診療所では、職員の大半が自家用車で通勤している。これまでA整形外科診療所は中途採用者の人材を多く採用しているが、今春、理学療法士のB男を新卒者として採用した。新卒採用はA整形外科診療所で初めてということもあり、職場の雰囲気は一気にフレッシュになり、活気が出てきた。
B男の勤務開始からしばらくたったある日のこと、C院長はB男から「1カ月ほど午後の勤務を休みたい」と勤務状況への配慮を求める相談を受けた。どうやら、大学卒業までに自動車学校を卒業できず、いまだに車の運転免許を持っていないため、自転車通勤をしているがつらく、早く運転免許を取得したいとのことであった。
C院長は「日曜日や祝日などの休日に自動車学校へ通えばいいのではないか」と返答したものの、日曜日や祝日は他の利用者も多いため予約が取りにくく、また平日の勤務による疲れを癒やすために休みたいという。自動車学校での教習の進捗もまだ路上教習にも進んでいない初期段階のため、午前中は通常勤務をし、午後は帰路の途中にある自動車学校に通いたく、1カ月ほど勤務時間を配慮してもらいたいとのことだった。
「社会人になったばかりとはいえ、何たる甘えたことを」とあきれたC院長は、感情を抑えながら顧問の社会保険労務士に相談をした。
給与条件や勤務免除期間の明確化が必須
顧問の社労士も「困ったものですね」と苦笑いしたものの、どうするかはC院長次第と述べた。正職員として働いている以上、そのような配慮はできないと突っぱねることもできるし、本人の要望を受け入れて午後の勤務を免除することもできる。その判断はC院長次第だが、突っぱねればそれを理由に退職する可能性もゼロではないとのことであった。
たしかに、C院長自身、最近の若い人の考えはよく分からないことも多く、B男が辞めてしまうのではと思えなくもない。事実、B男は学生時代にも様々なアルバイトをしていたものの、どこも長続きしていなかったようで一抹の不安がよぎる。4月から晴れて社会人となったものの、現在はA整形外科診療所で定める試用期間中で、まだ仕事への心構えや責任感などは醸成されていない。
一方、毎日遠方から自転車通勤しているB男の様子をC院長は見ており、B男のことが心配なのも事実だった。特に雨の日は大変そうで、本人もつらいだろうなどと考えていると顧問の社労士から、「仮に午後の勤務を免除するのであれば、給料や勤務状況といった様々な点を明確化した上で対応した方がいい」と助言を受けた。
例えば、(1)賃金の支給について不就労分は欠勤控除として扱うが、他の手当をどのように控除するのか、(2)直近に支給予定の夏季賞与はどう計算し支給するか、(3)退職金の計算時に午後出勤を免除した期間を出勤した1カ月として扱うか、(4)あらかじめ免許取得のための期間を1カ月と決めていたものの、それでも運転免許が取得できず延長したいと申し出た場合はどうするのか、(5)1カ月に満たない期間で運転免許証を取得できた場合、その1カ月を短縮するか──といったことを明確にしておくべきだという。
特に、賞与や退職金といった給与面で「出勤していたのに支給額が減らされているのはおかしい」と後からもめる可能性もある。従って、給与面の条件について、文書でも改めて明示すべきだと助言を受けた。結局、C院長は午後出勤を免除する具体的な期間を1カ月間と定めて、B男の要望を受け入れることとした。
その後、B男は無事に運転免許証を取得し、通常勤務に復帰することができた。C院長は、運転免許証くらい学校の卒業までに取得しているだろうと、何の疑いも持たなかったことを反省した。毎年2月下旬という理学療法士の国家試験の時期などを考えると、在学中に必ずしも運転免許を取得できるとは限らないことから、こういったケースにも備えておく必要があると勉強させられた。
(このコラムは、実際の事例をベースに、個人のプライバシーに配慮して一部内容を変更して掲載しています)
服部英治●はっとり えいじ氏。社会保険労務士法人名南経営および株式会社名南経営コンサルティングに所属する社会保険労務士。医療福祉専門のコンサルタントとして多数の支援実績を有する。
更新の情報が届くようになります。