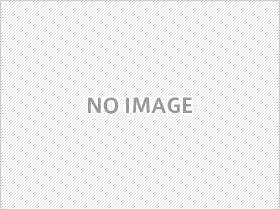Illustration:ソリマチアキラ
長年、自分の直観や経験を頼りに経営してきた。しかし、今どきは「データドリブン経営」が必要だ。収集・蓄積されたデータを分析し、その結果に基づいて戦略や方針を決めることをデータドリブン経営という(らしい)。
幸い、長作屋にはデータ分析にたけた人材がいる。レセコンも進化しており、さまざまなデータが瞬時に出せる。例えば、店舗ごとに人件費率や1人当たりの対応処方箋枚数など、薬剤師配置の参考となるデータも一目瞭然だ。そこでつまびらかになったのは、我が社の薬剤師1人当たりの1日対応処方箋枚数の少なさだ(泣)。
保険調剤では「40枚ルール」があるが、そんなのは夢の夢。長作屋の薬剤師の対応処方箋枚数はなんと1日18枚強!!!随分以前に手計算した時は25枚程度だったと記憶しているが、なぜかどんどん低下している。
その大きな要因は在宅だ。熱心に取り組んでいる店舗ほど、1人当たり枚数は少ない傾向にある。長作屋では早い時期に在宅医療に取り組み始めたが、当初は在宅対応できる薬局も少なく、患者宅が少し遠くても受けていた。連携する在宅医から、「輸液を扱える薬局がほかにない」と言われれば、多少遠くても受けるしかなく、それが大きな負担になっている。
現場の薬剤師に聞くと、片道30分、時間帯によっては1時間程度かかる訪問先もそれなりにあるという。明らかに車を運転している時間が長過ぎる。在宅は、面ではなくエリアで考える必要があるのだが、気付いた時には時遅しだ。
さらに先日、もう一つの理由に、偶然気付いてしまった。
きっかけは、ある店舗の業務終了後のレジ締めで金額が合わない“事件”だった。なぜか1万円が足りない。いくら探しても出てこない。患者に間違って渡したかと思い、カウンターに設置した過誤防止用のカメラや店内の防犯カメラのデータをダメ元で確認したところ、なんと薬剤師の手からするりと滑り落ち、投薬カウンターの隙間に消えていくお札の姿がバッチリ写っていたのだ。
おかげで“事件”は一件落着となったが、映像を早回しで見続けたことで面白いことに気付いた。薬剤師の動きだ。調剤室で薬剤調製したその次の瞬間には待合に出て患者に声をかけ、次には調剤室の奥に薬を取りに行くなど、とにかく動き回っている。忙しそうなのは分かるが、いかんせん無駄が多く、肝心の薬剤調製や患者対応といった調剤業務に従事している時間が明らかに短い。そして、調剤室の面積が広い薬局ほど1人当たりの処方箋対応枚数が少ない傾向にあることも分かった。
GPSを付けて薬剤師の動線を記録し、AI様にお願すれば、調剤室のレイアウトを最適化できるに違いないと思うものの、手っ取り早いのは、できるだけ移動距離を短くすることだ。半ば冗談、半ば本気でボクは現場の責任者に「調剤室の中央に調剤棚を集めて、ロープを張って、薬剤師が動ける面積を狭くしてしまえ」と伝えた(もちろん実行されていないが)。
ボクは長年、在宅機能を有し、薬剤師が快適に業務を行える広い調剤室や、ゆとりあるデザイン性の高い待合スペースを備えた薬局こそ理想だと信じ、そのような薬局づくりに力を入れてきた。だが、ふたを開けてみれば、それらが1薬剤師当たりの処方箋対応枚数を押し下げる要因となっていたのだ。とどのつまり、薬局はこぢんまりしているに越したことはないということのようだ。(長作屋)