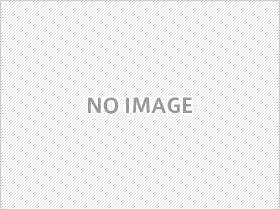「君の薬剤師免許は、私が絶対に守ってみせるから」。患者宅に向かう道すがら、隣の管理薬剤師Aにそう力強く言ったものの、ボクは内心、逃げ出したい気持ちでいっぱいだった。
事の始まりは、ある月曜日。いつものように出勤すると、Aが駆け寄ってきて、小児患者の鎮咳薬の量を間違えたと言う。薬を渡したのは先週金曜日で、今朝になって母親から電話があり、薬歴を見直してミスが発覚した。
母親が患児の異変に気づいたのは土曜日のこと。薬を飲んだ患児が、やけにハイになって興奮した状態で眠らなくなったようだ。母親が慌てて処方医に連絡したところ、診察時間外だったため、処方医は「念のため、飲んだ薬を持って、すぐに病院の救急外来を受診しなさい」と指示。その救急外来で、鎮咳薬が過量に投与されていたことが判明したというわけだ。母親はすぐに薬局に電話を掛けたが、誰も出なかったことにも怒っていた。
Aは、母親から掛かってきた電話への対応でもミスを犯した。「病院で薬の量が間違っていると言われた」という母親に、一応謝ったものの「それで、今はどんな状態ですか」と切り替えし、「今は落ち着いている」という言葉を聞くや否や、「なら大丈夫です」と言ってしまった。「薬の量を間違えておいて、『なら大丈夫』はないでしょう!」──火に油を注ぐとは、まさにこのことだ。
こうしたときは迅速に動くことが肝心。Aを連れて薬局を飛び出し、患者宅に向かう。「調剤ミスと土曜日に対応できなかったことを平身低頭してわびたら、すかさず後ろに下がって、後は私に任せろ!(キリっ)」。そして冒頭のキメぜりふ。カッコいい社長さんでありたいという心が、ボクにそう言わせていた。
患者宅の玄関で、いざ母親と向き合う。ただ、ただ、誠心誠意、謝るのみ。そして、大学病院の小児科の医師を紹介するので、受けられる検査を全て受けてほしいとお願いした。
そして次の日から私は、患児の様子を尋ねるという名目で、毎朝お宅に伺い、謝り続けた。しかし母親は、「将来、影響が出たらどうしてくれるのか。影響が出ないことを証明しろ」と、その一点張りだった。
影響が出ないことを証明しろ──。こういう無茶な要求をするのは、怒りが収まっていない証拠だ。人は、怒りが収まったとき、初めて建設的な話ができるようになる。誤解を恐れずに言うならば、お金の話ができるようになれば、解決の糸口が見える。ここで重要なのは、怒りが収まる前にお金の話をしてしまっては、火に油を注ぐ結果になるということ。タイミングが重要だ。
患児を診察した大学病院の医師は、「将来的に何も影響が出ないことを、医学的に証明するのは無理です。しかし、私の経験から、その心配はないでしょう。何か影響が残ることは考えにくい」と言ってくれた。グッドジョブだ。
毎朝通ううちに、少しずつ母親の態度が軟化してきた。そして2週間後の土曜日。その日は父親も家にいて、「今回の件で、仕事を休んだことが給与に響く」とボヤいた。今だ!
すかさず「お気持ちをお金に置き換えるのは大変失礼なことではございますが」と前置きした上で「法的根拠に基づいてお支払いさせていただきたい」と切り出した。
こうしてボクの朝の訪問は終了した。ふぅ。謝りに行くのはいつもボク……。社長業はラクじゃない。 (長作屋)
(「日経ドラッグインフォメーション」2013年9月号より転載)