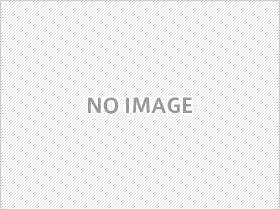イラスト:ソリマチアキラ
「友人は隣の薬局から処方箋1枚につき200円もらっている。200円とは言わないが1枚100円でどうだ?」—─。15年ほど前、隣のクリニックのA院長が、そう持ち掛けてきた。
「先生、それはできないですよ」と言った瞬間、「誰のおかげで薬局ができていると思っているんだ!」という怒り声とともに、ビールのコップが飛んできた。
A先生は医局人事で優遇されず、若い頃は地方の病院を回らされたようだが、地道に実績を重ね、大病院の糖尿病センター長の職責にあった。あのまま勤めていれば糖尿病専門医として著名になっただろう。本人も病院で専門性を極めたいと考えていたようだ。しかし、家庭の事情がそれを許さなかった。
A先生には4人の子どもがいて、奥さんが「全員、医者にする!」と言い張った。実際に開業当時、25歳の長男は2浪して地方の国立大医学部に入学し、まだ学生だった。2番目(女、23歳)は地方の私大医学部に、3番目(女、21歳)は東京の私大医学部に在籍、さらに末っ子(男、13歳)も医学部を目指して神戸の有名私立中学に通っていた。その学費や仕送りは莫大な金額だったろう。実家の援助なしに勤務医の給料だけで払えるものではない。
普段のA先生は、寡黙でジェントルマン、勉強熱心で素晴らしい人物だ。臨床医としての腕も良く、他の開業医から糖尿病患者を紹介されることも多かった。決して口数は多くないが、患者の評判も良かった。だが、仕事以外に趣味はなく、たまにお酒を飲むと泥酔し、グチが出る。テーマはいつも「オレの人生は一体何なのか」だ。
「本当は、開業なんかしたくなかった」というのがA先生の言い分で、「妻のために働かされ、子どものために働かされ、そして今は薬局を儲けさせるために働かされている。1枚100円は安いもんだ」と、グチとも脅しともつかないことを言い始める。
確かに先生が毎日100人近い患者を診てくれなければ、当社の経営は厳しかった。「薬局のために働いている」という先生の言い分は、あながち違っていない。「先生のおかげで仕事ができているのだから、それぐらいさせてもらいますよ」と言いそうになる気持ちをぐっと抑えて、「先生、それはできないよ。『薬局を儲けさせるため』なんて言わないで、患者のための医療を一緒にやりましょうよ」と、何とかその場を収めた。
それから10数年後、A先生は末っ子が医大を卒業するのを待っていたかのように、心筋梗塞で亡くなった。享年65歳という若さだった。お通夜に駆け付けたとき、「オレの人生は一体何だったのか。つまらない人生だったよ」という先生の声が聞こえたような気がした。
「それは違うよ。患者は先生を信頼していたし、うちの薬剤師は先生から医学に対する姿勢を学んだ。4人のお子さんも立派に育てた。閉じるのが早かったけど、悪い人生じゃなかったですよ」とボクは心の中でつぶやいた。
クリニックは長男が継承した。長男は医師としては決して悪くないが、患者にしてみると物足りないらしい。少しずつ患者が減り、今では1日30人を切っている。奥さんは薬局にやめられては困ると思っているようで、事あるごとに「息子を支えてやってくれ」と言う。
「A先生にお世話になって今があるのですから、何でもお手伝いしますよ」といい子ぶって言ってはいるものの、経営者としては暗い気持ちになる。義理を取るべきか、経営を取るべきか──。社長はやっぱりツラいのだ。(長作屋)