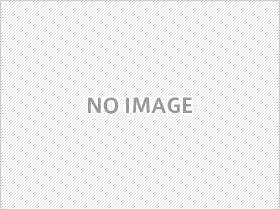経営者の心境としては、個人的な事情でお金を稼がなければならないのであれば、なぜ相談をしてくれなかったのかと思うもの。本人からの報告の前に他の職員から情報を得て立腹し、解雇をしたいと言う経営者もいる。
だが、そもそも診療所と職員との間では、「午前○時〜午後○時まで、クリニック内で××の仕事をしてもらい、その対価として△△円を支払う」という労働契約が締結されているはずであり、それ以外の時間帯については、基本的には制限を受けることがないと考えるべきである。つまり、日常生活のうち一定の時間・場所の拘束はするものの、それ以外の時間は自分の自由な時間と解釈すべきであり、その逆、つまり「当院で働くことが日常生活の主であり、それ以外の時間は休んでもよい」という解釈ではない。そのため、副業をすれば無条件に処分の対象にするといった対応は好ましいとはいえない。
ただし、中には、副業により疲労し本業に著しい支障を来すケースもある。また、仮にスタッフが副業で競合関係にある医療機関に勤務すると、患者情報や職員の処遇を中心とした経営情報の漏えいなどの懸念も生じる。こうしたマイナスの影響が生じたケースでは処分の検討の余地が出てくる。
通常は、地域内で診療時間帯を合わせているケースが多いので、競合施設での副業は考えにくいが、万が一副業が可能であれば、情報漏えいの可能性は否定できない。紙やデジタルによる資料の漏えいとまではいかなくても、職員間で何気なく口頭で伝えてしまうという程度のものは高い頻度で発生すると思われ、職員がまとめて他の診療所に転職してしまうというケースも現実的に発生している。
「本業への影響」はどの程度か?
今回紹介したケースでは、院長が当初解雇も視野に入れていた。副業を理由とする解雇の有効性を巡る裁判は過去に幾つも行われているが、「本業への影響がどの程度か」が大きな判断材料となっている。
例えば国際タクシー事件(福岡地裁1984年1月20日判決)では、タクシードライバーの従業員が通常の勤務時間以外に新聞配達の仕事をしていたことに対し、「安全運転に支障を来すのではないか」とのことでタクシー会社が解雇したものの、新聞配達で得ていた収入は高いものではなく、本業も熱心に支障なく遂行していたことから、解雇処分を無効とする判決が下されている。
他の労働裁判例(聖パウロ学園事件、大津地裁1999年3月29日判決など)に目を通しても、同様の結論となったケースは少なくなく、従業員の労務の提供が不能または著しく困難になる場合に限って解雇が可能と判断するのが妥当と考えられる。