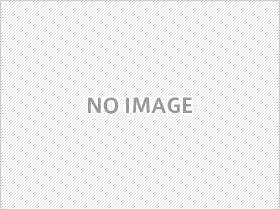しかし、人事評価制度を導入したことで新たなトラブルに見舞われるというのは、よくあるパターンである。B子のように、何らかの問題を抱える職員ほど自分自身を客観的に見ることができない傾向がある。「なぜ、自分ほど頑張っている人材がこれほどまでに評価が低いのか」ということで経営者に対して苦情を申し出て、同僚との関係もぎくしゃくしてくる。職場に嫌気が差して辞めてしまうことも少なくない。
他方で、コツコツと真面目に仕事をしている職員としては不満は解消されるが、果たしてこうした運用が本当によいのであろうか。いわゆる「問題職員」はともかく、さほど大きな問題もないような職員が、同僚より低めの評価をつけられたことを理由として辞めてしまうと、医院にとって損失となる。労働力人口が今後、確実に減少していく中、補充のための人材を確保することは容易ではない。最悪の場合、事業規模を縮小せざるを得ないということにもなりかねない。
経営者と職員のコミュニケーション阻害の懸念も
そもそも人事評価制度の導入に当たり、賞与などに差をつけること自体を目的とするのは好ましくない。人事評価は本来、経営者が職員に対して求めるものを評価項目として共有し、院長と職員との間で同じ方向にベクトル合わせをするための手法である。
例えば院長が、職員に対して「協調性」を保って仕事をしてもらいたいと考えるのであれば、「協調性」という項目を1つの評価指標と位置付ける。職員にもその指標を認識してもらえば、協調性を保つよう医院全体として意識して行動していくことにつながるため、人事評価制度そのものが否定されるものではない。
問題は、その使い方である。A診療所の場合は、賞与支給で差をつけることが目的となっていた上、人事評価項目の内容や評価結果を職員に周知していなかった。B子の心情を察すると、院長とは毎日のように顔を合わせている中で、自分が誤った認識をしていたのであれば、なぜ日々の業務の中で注意をしてくれなかったのか、なぜいきなり賞与を下げるという手段に出たのかと思うだろう。こうなると、院長と職員の間に感情的なしこりが生じ、コミュニケーションが阻害されてしまう。こうしたケースは非常に多いのが現状である。