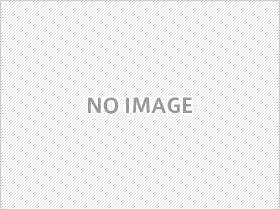注意しなければならないのは、その損害賠償の程度だ。労働裁判で有名な判例の1つに「茨城石炭商事事件」(最高裁1976年7月8日判決)がある。この事件では、タンクローリーを運転していたドライバーが前方不注意によって前の車に追突し損傷させたことに対して、会社が修理代を全額本人に求めたが、裁判所は請求額の4分の1が限度と判示している。
これは、必ずしも本人だけに責任があるとは限らず、事故防止に向けた会社側の配慮も問われることを意味する。つまり、そうした事故を招かないように安全教育はしていたのか、無理に運行をさせていないか、体力や健康面への配慮はどうであったのかといった点を勘案すると、本人に請求できるのは、せいぜい損害額の4分の1が限度ということである。もちろん、徹底して教育や管理をすれば、4分の1以上の金額を請求できる可能性はあるが、本人にも生活というものがあることを忘れてはならない。
今回のケースでも、損害額の全額をスタッフに負担させるとトラブルになる恐れがある。タブレット端末にクッション性のあるカバーが取り付けられていたのか、仮に外の地面で落としたのであれば外での使用を禁止するルールがあったのか、私的なことでタブレット端末を使っていたのであれば業務外利用を禁止するルールが存在していたのかといった点も勘案する必要がある。労働基準法の根底にあるのは労働者保護という考えなので、職員が労働基準監督署などに相談した場合、損傷の予防策や使用ルールの不備など経営者に不利な要素があぶり出されることも十分考えられる。
ルールが職員に周知されているか?
さらに注意をしなければならないのは、そういった損害の賠償を求める際のルールが職員に十分に周知されているのかということである。就業規則において「損害賠償を求めることがある」と定めるケースは多いが、その就業規則が院長の机の引き出しに入ったままで職員に周知されていなかったり、そもそも職員数が10人未満で作成義務がなくルールが存在していない場合には、労使間でトラブルになりやすい。
そのため、スタッフの損害賠償のルールを策定して運用するのであれば、損害賠償を求めることがある旨を就業規則に明確に定めて周知しておきたい。職員数10人未満で就業規則がない医療機関では、採用時の誓約書にその旨を記載しておくのも一法だ。ただし、ルールがあるからといって、頻繁に適用していると職員は萎縮してしまい、全体のパフォーマンスが低下したり定着率が下がってしまうこともある点には注意しておきたい。
今回紹介したA診療所では、就業規則は存在するものの、損害賠償についての規定は特に設けられていなかった。知人に紹介された社会保険労務士に院長が相談したところ、就業規則の規定がない以上、賠償に関して強気の姿勢を貫くのは好ましくないとのことだった。そこで、B子に対してはその旨を正直に伝えた上で、賠償を求めるのは控え、就業規則の見直しに着手することにした。
(このコラムは、実際の事例をベースに、個人のプライバシーに配慮して一部内容を変更して掲載しています)
服部英治●はっとり えいじ氏。社会保険労務士法人名南経営および株式会社名南経営コンサルティングに所属する社会保険労務士。医療福祉専門のコンサルタントとして多数の支援実績を有する。