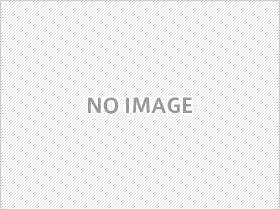後日、院長と夫人は地元の社会保険労務士に相談し、以下の説明を受けた。
(1)2019年4月1日施行の改正労働基準法により、有給休暇が年10日以上付与される職員については、5日以上取らせることが事業主の義務になる(制度改正の解説記事はこちら)。
(2)(1)の法改正はパートにも適用される。
(3)今までのように、各自に出勤したい日を申告してもらってシフトを組む方法ではなく、例えば「○○さんは月、水、金に出勤」といったように、原則として曜日または月の労働日数を決めた方がよい。そうすることで、有給休暇の付与日数をあらかじめ計算し、取得に向けた計画を立てやすくなる。
(4)お盆の時期と年末年始に、有給休暇の計画的付与をするとよい(労使協定が必要)。
(5)最近は、退職前に有給休暇をまとめて使い切る人が増えているが、在職中に計画的に消化してもらった方が経営者、スタッフ双方のために良い。
院長と夫人は社会保険労務士のアドバイスを受け、職員ミーティングで、有給休暇の日数を記した書面を渡した。そして、各自の付与日数のうち5日を超える分の日数をお盆と年末年始の休診日に充てる労使協定を結んだ。同クリニックでは、それまで年末年始などの時期を「特別休暇」としておらず、休診期間中の賃金が支払われることはなかった。これを有給に変更した形だ。また、シフトの組み方を原則、曜日固定制とし、有給休暇を取りたい場合は、前月までにシフト表に記載するルールとした。
この仕組みを導入した当初、A院長は「果たしてうまくいくのか」と不安を抱いていたが、職員たちはこれまで通りお互いに配慮しながら休暇を取得しており、シフトが組めなくなるような事態は発生していないという。
排除するのではなく…
診療所の労務管理は、院長の労働関連法令の理解度や運用に対する考え方に左右されやすい。中には、スタッフが有給休暇を十分に取得できなかったり、今回のケースのように「パートには有給休暇がない」と誤解している例も見られる。
そうした診療所に、労働基準法などの知識を持ち、自らの権利をきちんと行使したいと考えるスタッフが入職することで、院長が対応を迫られるというのはよく見られるパターンだ。特に最近は、インターネットを通じて労働基準法などの知識を容易に得られるようになったことで、休暇や労働時間などのルールをよく理解した上で求職してくる人が目立つようになっている。
対応を迫られた院長の反応は様々で、中には、当の職員を排除しようとするケースもある。だが、そうした対応をすると、既に在籍しているスタッフたちからも反感を買うことになりかねない。前述のように、働き方改革の一環で有給休暇の取得が義務化されるなど、今後クリニックは様々な形で労働環境の改善を迫られることになるとみられる。新入職員から要請や提案があり、それが妥当なものであれば、きちんと受け止めて改善につなげていきたいところだ。
(このコラムは、実際の事例をベースに、個人のプライバシーに配慮して一部内容を変更して掲載しています)
加藤深雪(特定社会保険労務士、社会保険労務士法人 第一コンサルティング代表)●かとう みゆき氏。日本女子大人間社会学部卒業後、2003年第一経理入社、2018年10月より現職。企業や医療機関の人事労務コンサルティングを手掛け、中小企業大学校講師や保険医団体の顧問社会保険労務士も務める。