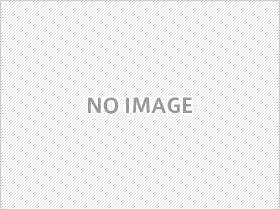イラスト:畠中 美幸
今回はトラブル事例ではないが、1人のスタッフの入職を契機として、年配医師が経営するクリニックの労務管理が大きく変わったケースを紹介したい。
このクリニックは北関東に立地し、A院長が30年近く経営してきた。開院した当時は周辺地域に若い世代の家族も多く、賑わっていたが、最近は大都市部に出ていく人が増えて、人口がめっきり少なくなってきた。
それに伴い患者数も減少。自分の体力が衰えてきたこともあり、A院長は診療時間を減らし、スタッフ数も減らしてきた。ピーク時には看護師、事務職員を合わせ常勤5人、パート4人を雇っていたが、現在のスタッフ数は5人で、全て有期雇用のパート契約をしている。5人はいずれも近所に住む主婦。人間関係は良好で、それぞれの子どもの学校行事の際は、お互いに譲り合ってシフトを組んでくれている。A院長としては、自分のリタイアまで、このまま平穏に日々が過ぎていくものと思っていた。ところが昨春、看護師のB子が入職したことで、クリニックの運営に変化が生じた。
B子の採用は、熟練看護師C美の勤務日数減少に伴うものだった。C美はそれまで、パートとはいっても週5日の勤務をこなしてくれていた。大学病院の手術室で勤務していただけあって仕事の手際が良く、クリニックの中心的なスタッフとして院長の信頼も厚い。
そのC美が、子どもの受験があるので勤務時間を週2日程度に減らしてほしいと申し出た。C美の入っているコマを埋めるためには、新たに看護師を採用しなければならない。昨今の看護師の採用難について周りから聞いていた院長は「困ったことになった」と思ったが、要望を受け入れ求人を出すことにした。条件は、週3~4日勤務のパートで、時給は相場を見て1600円とした。
パート職員にも有給が必要とは知らず…
しばらくするとB子から応募があり、院長は早速会ってみることにした。B子は40代前半で、都内の病院に勤めていたが、離婚を機にUターン。子どもが2人いて、シングルマザーとして育てていくため、時間の融通が利くパートの求人を探していたのだという。院長は、今いるスタッフも子育て中の主婦が多く、協力しながらうまくやっていけそうだと思い、B子を採用することにした。
それから5カ月が経過したところで、院長はB子からこう尋ねられた。「院長、私は入職してから来月で半年になりますので、有給休暇がもらえるはずです。来月、子どもの運動会に合わせて有給休暇を取りたいので、日数を教えてください」。
A院長は、常勤職員を雇っていたころは、有給休暇を労働基準法の規定通りに付与していた。だが、今は全員パート職員で、そもそもパートでも有給休暇を付与する必要があることを知らず、取得実績ゼロの状態が続いていた。
そのため、夫人に労働基準監督署に問い合わせてもらい、パートへの有給休暇の付与の必要性と日数について確認をした。すると、B子の言うように、採用してから半年が経過し、その間に全労働日の8割以上の出勤をしている場合は、パートであっても常勤と同じように有給休暇を与えなければならないとの回答を得た。ただし、パートの場合は、週の労働日数によって比例的に付与日数が変わるという。B子の場合は年に7日間の有給休暇が発生することが分かり、院長はその取得を認めた。
他のスタッフからも有給の質問が
それからしばらく経ったころ、他のスタッフたちが「院長、B子さんから聞いたのですが、私たちも有給休暇が取れるのですか」と質問してきた。院長は、「確認するから、しばらく待ってほしい」と答え、夫人に各スタッフが取得可能な日数を調べてもらった。すると、週3日勤務で勤続年数が最も長いスタッフの場合、年間11日になるという。有給休暇は1年持ち越し可能で、そのスタッフは前年に全く取得していないためプラス10日、年間計21日となることが分かった。
これをフルに取得されたらシフトが回らなくなるし、複数のスタッフが同じ日に取りたいと言ってきたらどうするのか——。A院長は頭を抱えてしまった。