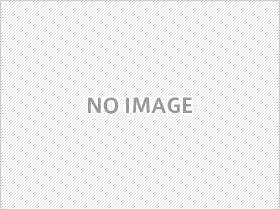また、労働基準法第21条では、解雇予告手当を支払わなくてもよい労働者として次の者を挙げている。
(1)日々雇い入れられる者
(2)2カ月以内の期間を定めて使用される者
(3)季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者
(4)試の使用期間中の者
職員を解雇するには、少なくとも30日前に予告することが原則であり、即時解雇であったり予告期間が30日に満たない場合は、解雇予告手当を支払う必要がある。
上記(4)だけを見れば、「試の使用期間中の者」は解雇予告手当が必要がないと読み取れる。しかし、同法では(4)の「試の使用期間中の者」については、14日以内であれば解雇予告手当が不要である一方、その期間を超えれば支払いが必要であるとしている。そのことを知らずに、「試用期間中であれば一切解雇予告手当は不要である」とか、「14日以内であれば自由に解雇ができる」などと考えている経営者が少なくないのが現状だ。
「求めるレベル」をどの程度に設定するか?
とはいえ、試用期間は、採用された人材が自院で今後働くに当たってふさわしいか否かを確認する期間であり、法律用語を用いれば、その期間は「解約権を留保された労働契約」ということになる。従って、この期間は通常の雇用期間と異なり、解雇を緩く考えることができ、どうしても自院に合わないということであれば、解雇をすることの有効性が高まるものと考えることができる。
しかし一方で、その基準として厳しすぎることを求めている医療機関も少なくなく、その結果、ベテランと採用されたばかりの新人しかおらず、中堅職員が残っていないというケースもある。そのため、「求めるレベル」という点にも注意を払わなければならない。
労働裁判例を紐解くと、「ファニメディック事件」(東京地裁2013年7月23日判決)では、顧客に対する請求ミスの繰り返しや、勉強会参加の面での協調性の欠如を理由として、試用期間満了に伴い解雇したことが有効かどうかが争われた。
このケースでは、請求ミスそのものは3回程度、書類記載不備が2回程度で、その後も繰り返されているわけでもなく、勉強会への出席について明確な業務指示が出されたわけではないなどの理由によって、裁判所は社会通念上相当とは認めず、留保解約権の濫用として解雇を無効とした。