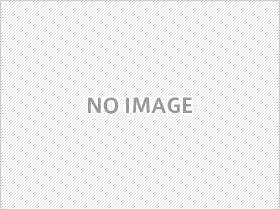他方で、同僚などとの協調性が乏しく、業務修得への熱意や責任感が感じられず、これが改まることを期待して試用期間を延長したものの、その態度などが改まることなく逆に問題行動を起こしたため解雇をしたことを有効とした労働裁判例(松江木材事件、松江地裁1971年10月6日判決)もあり、期待水準を明確化し、それを伝達することは、試用期間中の職員の労務管理において極めて重要なポイントとなる。
試用期間専用の雇用契約書を取り交わす
ただ、医療機関ではそれ以前に、上司や先輩がキチンと仕事のやり方を教えず、たまたまいろいろと気付くことができる職員を「よくできる職員」、そうではない職員を「できない職員」と区分してしまい、できない職員は教えられないことでさらにミスを繰り返し、管理者が解雇を考えるというケースが散見される。これは、本人に問題があるというよりも、管理者に問題があることも考えられ、何も教えられない本人は不幸でしかない。
そもそも、試用期間という制度があるのならば、解雇のときに「“試用”なのだから」という理屈を持ち出すだけではなく、その制度を最大限活用していくべきだろう。つまり、「解約権を留保された労働契約」であれば、使用期間中に達成してもらいたい能力や行動などを明確に伝え、それが達成できれば「本採用」といった手続きを踏んでいくべきである。
言い換えれば、自動的に本採用となるのではなく、試用期間中には試用期間専用の雇用契約書を取り交わし、その契約書の中に期待される能力などを明確化。同時に、定期的な面談を通じてその達成度合いを確認し、試用期間中にそれらが達成されれば、改めて「本採用」用の雇用契約書で締結する、といったステップを踏めば、試用期間中であるから解雇を考える、といった発想は生じないのではないだろうか。
(このコラムは、実際の事例をベースに、個人のプライバシーに配慮して一部内容を変更して掲載しています)
服部英治●はっとり えいじ氏。社会保険労務士法人名南経営および株式会社名南経営コンサルティングに所属する社会保険労務士。医療福祉専門のコンサルタントとして多数の支援実績を有する。