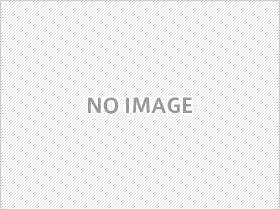——そこはどんな病院だったのですか?
県外にある100床程度の病院でした。外科も診療科目にあったのですが、あまり手術に積極的でなく、年々手術件数も減り、老人病院化していました。そんな状況でしたから、医局メンバーはその病院へ行きたがらなかった。私も最初は週1回の診察と当直に行くだけだったのですが、うちの医局は20人と小所帯で人繰りに困っている様子だったので、いつからか率先して行くようになり、気付けばそこがメーンになっていました。
私が常駐する頃には手術はほとんど実施されず、仕事といえば、術後のフォローや下肢静脈瘤、リンパ浮腫など、外来だけで処置ができる疾患が大半。外科医として、手術の腕を磨く場にはなり得ませんでしたが、私はむしろ充実した毎日を送っていました。
元来、私は人と話をするのが好きなんです。上長から「診察時間が長い」とよく注意されていたぐらいで。その個人病院での勤務を続けるうちに、お年寄りとじっくり話をしながら診察をするのが、性に合っていることに気づきました。そして、手術をして病気を治す医師も重要だけど、疾患のことや家族のことなどを色々話しながら治療をする医師も必要だと考えるようになりました。
また、手術から遠ざかるうち、「大学へ戻って執刀医として術場に立っている自分」が想像できなくなってしまい…。もし自分が患者だったら、腕の良い医師が執刀してきれいに縫ってほしいと思います。そう考えたとき、私よりも上手に手術ができる外科医がいるのに、私がわざわざ執刀するのは患者に対して申し訳ない。「もうあかん、これは外科医を続けていけんな」と思うようになりました。
そうなると、この医局にいる意味がないので、医局の人事ローテーションから外れ、個人病院の勤務医になりました。私が入局した当時の教授はすでに退官していましたから、辞めることに関して医局側からは特に何も言われませんでした。
——その個人病院も辞めて、大学院に入学された理由は?
実は、個人病院で多くの患者さんに接するうちに、自分の考えが少し変化してきたのが理由です。医師として病気を治すことはもちろん大切だけど、それ以前の、病気になる前に何らかのケアができないかと。「できるだけ医師が要らない世界をつくりたい」という意識が強くなり、今度は公衆衛生の分野を勉強したいと思うようになりました。
結局、その個人病院には医局からの派遣時代を含めて10年ぐらいお世話になりましたが、4年前の大学院入学を機に退職しました。そして3年前からは、一度その大学院を休学して保健所の職員として働いています。大学院の先生から「今、保健所の職員の席が空いているけど、どう?」と勧められことがきっかけです。本当は40歳までという年齢制限があったのですが、特別に45歳までに上げてもらい、何とか試験を通りました。
保健所では、感染症対策の担当者として日々奔走しています。感染の届け出に基づいた調査を実施したり、感染症対策のマニュアルを作成したりしています。最近では鳥インフルエンザの対応に追われて大変でした。また、地域住民向けの健康講座などで話すこともあります。
こうした仕事に、とてもやりがいを感じています。何らかの問題に対して策を練り、方向付けをして「こっちに向かっていきましょう」と、みんなを引っ張っていくということが好きなんだと思います。
保健所の活動は、医師や医療機関との連携抜きには語れません。私は双方の内情を熟知する立場として、うまくつなげる立場になりたいと思っています。年収は医師時代の6割程度になりましたが、不満はありません。個人病院だと辞めた後の保障はありませんが、今は公務員なので退職金や年金などが手厚く、その面では安心しています。