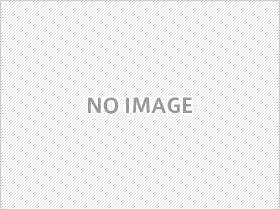ブラック・ジャックにあこがれ外科医を目指す。外科の中でもまだまだ発展の余地が大きい移植外科の道を志し、国内外の病院で研さんを積む。「うちの病院に移植外科を立ち上げてくれ」という、ある院長の誘いに応じて転職。しかし、出勤初日にもらった辞令にはなぜか「救急科」と書いてあった…。

黒田悟志(仮名)さん
1994年に国立大学医学部を卒業後、出身大学の外科医局に入る。関連病院で主に消化器外科の経験を積んだのち、大学病院や海外の病院で肝移植の他、腎移植、膵移植に携わる。約10年に及ぶ医局生活の後、A病院へ転職。さらに移植外科医として腕が振るえる場所を求め、B病院に移る。現在はB病院で、腎移植、腎不全外科全般を担当。40代、妻と一男一女、義母の5人暮らし。
——なぜ、移植外科医を目指されたのですか。
子供の頃、手塚治虫の『ブラック・ジャック』を読んで子供ながらにその生きざまに共感し、小学校4年生のときには外科医になろうと決めていました。小学校の卒業文集にも「外科医になりたい!」と書いていたほどです。
大学卒業時に、外科の領域でも移植外科医になろうと決めていました。それは、移植はその当時、一部の医師、医療機関しか手掛けておらず、未完成の部分がいくらでもあるという印象だったからです。「僕でも活躍できる可能性は大きそうだ」と思いました。それに、『ブラック・ジャック』を読み返してみると、非常にたくさん移植のシーンがある。“移植願望”は、実はここで刷り込まれたのかもしれません。
大学卒業後は母校の外科医局に入りましたが、すぐに移植などできるはずがなく、初期研修後は関連病院で消化器外科の経験を積みました。その病院には3年ほどいましたが、食道がんや膵臓がん、胆管がんなど消化器外科で手掛ける手術を一通りやらせてもらったと思います。外科医の世界は徒弟制の印象があると思いますが、僕がいた医局では若手にもどんどん経験を積ませてくれました。今から思うと、ありがたかったですね。
そうこうするうちに母校でも生体肝移植が実施されることになり、部長へ「僕もぜひやらせてほしい」と直談判し、移植に関連した医局に帰局する形で、大学病院の移植チームに加わらせてもらいました。その後は腕を磨くべく、海外の病院へ武者修行に行ったんです。
——海外の病院はいかがでしたか。
その病院では、年間100例ほどの肝臓、膵臓、腎臓の移植手術、そして脳死ドナーの手術を手掛けました。そこで学んだのは、移植は多くのスペシャリストが連携して初めて実施できるということです。外科医や内科医だけじゃない、感染症や精神科の医師、クリニカルナーススペシャリスト、移植コーディネーター、ソーシャルワーカーなどが互いに協力し合いながらも、それぞれがプロ意識を持ち、自身の役割をきちんとこなしていく—。そういう姿を目の当たりにして、これを自分の医療のスタイルにしたいと強く思いました。
海外に行って1年が過ぎた頃でしょうか。移植外科の教授が変わり、その先生から「そろそろ帰って来い」という電話がかかってきたんです。そのとき僕は「今後こんな医療がしたい」と自分の夢について語りました。すると、教授はそれを遮り、「おまえは医局のメンバーの1人として、私の言うとおり働けばいいんだ!」と言ったんです。教授とはかつて、ある病院で一緒に働いた経験があり、そのときの印象もあって、この言葉をきっかけに僕は大学医局を離れることに決めました。
「申し訳ありませんが、あなたと一緒に仕事はできない。僕は医局に戻りません」と言うと、その教授は面食らっていたようでした。その後も再度電話をかけてきたのですが、丁重に断りました。
海外で外科医として働いた経験は僕にとって非常に大きな財産です。移植医療にどのように携わっていくのかというビジョンを持つことができたし、自分の腕が日本以外でも通用することも実感できた。だからこそ、医局に頼らなくても自分の力でやっていけると思えたんです。